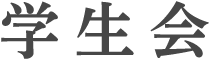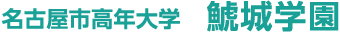
メニュー

史跡散策Historic Site Walk
第12回校外活動 野間大坊散策
2025-01-30
今回は、知多半島の先端にある野間大坊を中心に散策しました。野間大坊は通称で、正式には鶴林山大御堂寺(かくりんざんおおみどうじ)と言います。お寺の歴史は古く天武天皇(673~686)の時代に「阿弥陀寺」として建立され、その後「大御堂寺」と称されました。のちに源義朝がこの地で謀殺され、それを供養するために源頼朝が七堂伽藍を造営します。本尊様が源頼朝の願いを叶えたことから、祈願成就・開運の寺として有名です。平治の乱で敗れた「源義朝」がこの「大御堂寺」のある野間へ家臣を頼ってやってきたのですが、その家臣(長田忠致・景致)の裏切りに遭い、湯殿で殺されてしまいました。「我に木太刀の一本でもあればむざむざ討たれはせん」と無念の死をとげた義朝公のため、その墓には木太刀が奉納されています。
※クリックすると拡大することができます。
源義朝は法山寺の湯殿で入浴中に殺されました。法山寺の入り口にある乱橋は、源義朝の家来と、長田氏の家来が戦った所と伝えられています。血の池は、義朝公の御首を洗った池で、国家に一大事があると池の水が赤くなると言い伝えられていて、これまでに一度赤くなったことがあるそうです。その後長田父子は源氏側につき、頼朝から「勲功があったなら美濃と尾張を与える」と言われていたのだとか・・・。しかし、1190年の上洛途上で尾張国野間に立ち寄った頼朝は、手柄をたてた長田忠致・景致父子に恩賞を与えるといって誘い出し、松の木に磔(はりつけ)にして殺したといわれています。長田忠致は辞世の句として「嫌へども命のほどは壱岐(生)の守 身の終わり(美濃・尾張)をぞ今は賜る」を詠んだと言われています。古より洒落は好まれていたのでしょうか。
※クリックすると拡大することができます。
大御堂寺本堂の御本尊は「木造阿弥陀如来坐像」で愛知県指定重要文化財となっています。木造阿弥陀如来立像も安置されており、快慶の作品です。これも愛知県指定重要文化財となっています。野間大坊客殿の御本尊は「開運延命地蔵尊」で仏師定朝作といわれています。平清盛の継母の「池禅尼」より賜ったもので、このお地蔵様を拝んで拝んで拝み抜いた頼朝公は、望みがかない鎌倉に幕府を開くことができました。このことから「開運延命地蔵尊」には不思議なご利益があり、どんな願いでも叶えてくれるといわれています。何度も何度もしっかりと願うことで大願成就となるのであれば、この世も平和で幸いなのですがね。さて、散策が終わって解散となった後はランチを頂くのに良い時分です。今回は見るからに美味しそうな海鮮ランチでした。
※クリックすると拡大することができます。